話題の【腸内フローラ】とは?腸内環境を整える具体例までを徹底解説します!
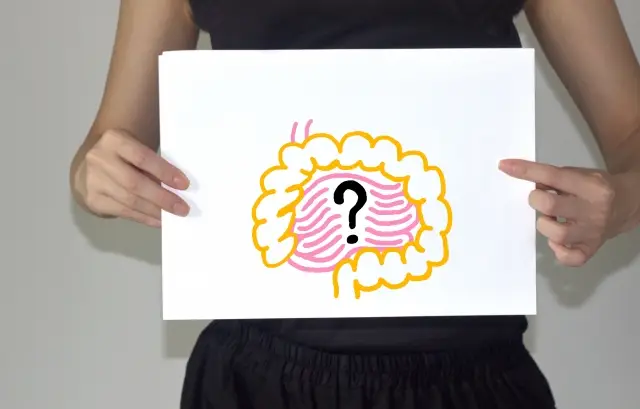
突然ですが、皆さんは【腸内環境】を意識したことはあるでしょうか?
健康を意識しているという方だと特に【腸内環境】は重要なひとつの項目になっているのではないでしょうか?
そこで今回は【腸内フローラ】について徹底解説をしていきます。
今まで
- 【腸内環境】を意識したことがあるという方も、ないという方も
- 【腸内フローラ】を意識したことがあるという方も、ないという方も
気になるという方は是非、最後までご覧ください!!
▼この記事を読んで欲しい方
- 腸内環境を日ごろから意識している方
- 腸内環境を気にしている方
- 日ごろから腸内環境を整えている方
- 腸内フローラを意識している方
- 腸内フローラについて詳しく知りたいと方
- 腸内フローラについてよく分からない方
- 身体の中からキレイになりたい方
- 身体の中から健康になりたい方
▼この記事を読んで分かること
- 腸内フローラの構成について
- 腸内フローラの主な機能と役割について
- 腸内フローラの変動因子について
- 腸内フローラの乱れはなぜ起こるのか?
- 腸内フローラの乱れの原因について
- 腸内フローラの乱れと疾患の関係性について
- 腸内フローラの解析技術について
- 腸内フローラの乱れを改善するための食事療法について
腸内フローラの構成
Phylum「腸内フローラ(腸内細菌叢)」とは、ヒトや動物の腸管内に生息する微生物の集団のことで、特に細菌を中心に、ウイルス・真菌・古細菌など多様な微生物が含まれています。
腸内の微生物がまるで花畑(flora)のように多種多様に存在することから、この名称が使われています。現在では、より正確な表現として「腸内マイクロバイオータ(gut microbiota)」や、それらの遺伝情報を含めて「腸内マイクロバイオーム(gut microbiome)」と呼ぶことも増えています。
1.主要な細菌門(phylum)
腸内における主要な細菌群は主に以下の5門(phylum)に分類されます。
| 細菌門 | 特徴 |
|---|---|
| Firmicutes(ファーミキューテス門) | グラム陽性、クロストリジウム属やラクトバチルス属など。短鎖脂肪酸の産生。 |
| Bacteroidetes(バクテロイデーテス門) | グラム陰性、Bacteroides属。多糖の分解に関与。 |
| Actinobacteria(アクチノバクテリア門) | ビフィズス菌(Bifidobacterium)など。幼児の腸内で優勢。 |
| Proteobacteria(プロテオバクテリア門) | 大腸菌(Escherichia coli)など。炎症状態で増加することがある。 |
| Verrucomicrobia(ヴェルルコミクロビア門) | Akkermansia属。腸粘膜の保護と代謝に関与。 |
腸内フローラの主な機能と役割
1.代謝機能
難消化性食物繊維やオリゴ糖を発酵 → 短鎖脂肪酸(SCFA)(酢酸・プロピオン酸・酪酸など)を産生。
短鎖脂肪酸は
結腸上皮細胞のエネルギー源
炎症抑制作用
腸管バリア機能の維持
インスリン感受性の向上
2.免疫調整
腸管免疫系(GALT)の発達と維持に寄与。
Treg(制御性T細胞)の誘導、炎症性サイトカインの調節。
常在菌が自然免疫と獲得免疫のバランスを整える。
3.病原菌からの防御(コロニゼーション・レジスタンス)
常在菌が腸内に住み着くことで病原菌の定着を防ぐ。
競合排除(栄養源・受容体・スペースの奪い合い)。
4.神経系との関連(腸ー脳相関)
腸内フローラは神経伝達物質(GABA、セロトニンなど)の産生に影響。
迷走神経や免疫系を介して中枢神経系に信号を伝達(腸脳相関)。
うつ病や不安障害、自閉症スペクトラムとの関連が研究中。
腸内フローラの変動因子
腸内フローラの構成は個人によって大きく異なり、以下の因子により変動します。
| 因子 | 影響内容 |
|---|---|
| 出生時の分娩様式 | 自然分娩 vs 帝王切開で構成が異なる(母体腟由来菌 vs 皮膚菌)。 |
| 授乳方法 | 母乳 vs 粉ミルク:母乳にはビフィズス菌増殖因子が含まれる。 |
| 年齢 | 新生児期から老年期にかけて徐々に変化。 |
| 食生活 | 食物繊維の多い食事は多様性を促進。高脂肪食は炎症性菌増加。 |
| 抗生物質 | 一時的なディスバイオーシス(菌叢の乱れ)を起こす。 |
| ストレス | 腸の運動・分泌に影響し、菌叢構成も変化。 |
| 運動・睡眠・環境 | 健康なライフスタイルが多様性を維持。 |
腸内フローラの乱れ(ディスバイオーシス)
「ディスバイオーシス(dysbiosis)」とは、腸内フローラのバランスが崩れた状態です。以下の疾患と関係が報告されています
炎症性腸疾患(IBD:潰瘍性大腸炎、クローン病)
過敏性腸症候群(IBS)
メタボリックシンドローム(糖尿病、肥満)
自閉症スペクトラム障害(ASD)
パーキンソン病、アルツハイマー病
アレルギー、自己免疫疾患
精神疾患(うつ病、不安障害など)
腸内フローラ解析技術
腸内フローラの研究には以下のような技術が使われます:
1.16SrRNA遺伝子解析
細菌のリボソームRNAの一部をPCRで増幅し、配列決定。
属レベルまでの分類が可能。コストが安いが解像度はやや低い。
2.メタゲノム解析
全DNAを網羅的に解析。種レベルの同定や機能予測が可能。
高コスト・高解析能力が必要。
3.メタボローム解析
微生物が産生する代謝物(短鎖脂肪酸、ビタミンなど)を網羅的に解析。
実際の機能的影響を把握。
腸内フローラは単なる細菌の集合ではなく、消化・免疫・神経・代謝に深く関わる、いわば「もう一つの臓器」とも言える存在です。近年ではプレバイオティクス・プロバイオティクス・ファージ療法・FMT(糞便微生物移植)などによる腸内フローラの制御も注目されています。
ディスバイオーシスとは?

腸内フローラ(腸内細菌叢)の乱れ(ディスバイオーシス / dysbiosis)は、全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性がある重要な現象です。以下では、腸内フローラが乱れる原因について、科学的根拠に基づきながら、徹底的かつ専門的に解説します。
ディスバイオーシス / dysbiosisとは、腸内フローラの多様性が低下したり、有害菌が増加、有益菌が減少したりして、腸内の微生物バランスが崩れた状態のことを指します。
腸内フローラが乱れる主な原因とそのメカニズム
1.抗生物質の使用
〇概要
抗生物質は病原菌だけでなく、腸内の善玉菌(例:ビフィズス菌、ラクトバチルス属)まで広範に殺してしまう。
〇メカニズム
広域スペクトル抗生物質(例:セフェム系、マクロライド系)は腸内の常在菌も殺菌。
善玉菌の減少によりクロストリジウム・ディフィシル(C. difficile)などの病原性菌が異常増殖。
乱用・長期使用ほど深刻なディスバイオーシスを引き起こす。
〇補足
抗生物質の影響は短期的には数週間〜数ヶ月、長期的には1年以上残る場合もある。
2.食生活の乱れ(低食物繊維・高脂肪・高糖質)
〇概要
偏った食生活が善玉菌のエネルギー源を断ち、悪玉菌の優位を招く。
〇メカニズム
水溶性食物繊維やプレバイオティクスの不足 → 短鎖脂肪酸(酪酸など)産生菌の減少。
動物性脂肪・加工食品の過剰摂取 → ビリ酸の過剰分泌により炎症性細菌(Bilophila wadsworthiaなど)が増加。
高糖質食 → 炎症促進性のファーミキューテス門が過剰に増加する傾向。
〇研究例
高脂肪・低繊維食を与えたマウスでは腸内の多様性が減少し、代謝疾患(肥満・糖尿病)のリスクが上昇。
3.慢性的なストレス
〇概要
心理的ストレスが腸の機能に影響し、腸内環境の悪化を引き起こす。
〇メカニズム
視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)が活性化 → コルチゾール上昇 → 腸管バリア機能低下。
腸管透過性(leaky gut)が高まり、炎症性反応が誘導される。
ストレスによって酪酸産生菌や乳酸菌が減少し、プロテオバクテリアが増加することが報告されている。
4.加齢
〇概要
年齢とともに腸内フローラは構成が変化し、多様性が失われやすくなる。
〇メカニズム
高齢者ではビフィズス菌の減少、クロストリジウム属やプロテオバクテリアの増加が見られる。
免疫機能の低下、腸蠕動の減退、食事量や内容の変化が影響。
〇補足
一部の研究では、長寿者の腸内フローラは若年者に近い多様性を維持している場合がある。
5.睡眠不足・概日リズムの乱れ
〇概要
体内時計の乱れが腸内フローラにも波及する。
〇メカニズム
腸内フローラは概日時計と連動し、一定のリズムで変化している。
睡眠不足・夜勤労働・時差ボケなどでリズムが崩れると、腸内の多様性低下・悪玉菌の増加が起きる。
メタボリックシンドロームとの関連も。
6.運動不足
〇概要
適度な運動は腸内細菌の多様性を促進する。逆に運動不足は腸内環境を悪化させる。
〇メカニズム
運動によって酪酸産生菌(例:Faecalibacterium prausnitzii)が増加する。
逆に座りっぱなしや不活動は炎症性細菌の増加と関連。
7.腸疾患や消化器系のトラブル
〇概要
IBS(過敏性腸症候群)やIBD(潰瘍性大腸炎・クローン病)などでは、腸内フローラが根本的に乱れる。
〇メカニズム
IBD患者では抗炎症性菌(例:F. prausnitzii)の減少、病原性プロテオバクテリアの増加が報告されている。
腸炎により腸上皮が傷つき、病原菌の侵入が進行。
8.環境因子・化学物質への曝露
〇概要
食品添加物や殺菌剤、農薬、重金属、微小プラスチックなども腸内環境に影響を与える。
〇メカニズム
例:人工甘味料(サッカリン、アスパルテーム)は腸内フローラを変化させ、糖代謝異常を引き起こす。
界面活性剤(乳化剤)は腸管バリア機能を破壊し、炎症を促進。
マイクロプラスチックの摂取が腸内の細菌組成に悪影響を及ぼす報告も。
9.感染症・ウイルス感染
〇概要
特定のウイルス感染(例:ノロウイルス、ロタウイルス、COVID-19)でも腸内フローラが急激に乱れる。
〇メカニズム
腸の粘膜破壊、免疫応答の異常により善玉菌が減少し、病原性細菌や真菌の異常増殖を招く。
補足:ディスバイオーシスの種類
多様性の減少型(Loss of diversity)
- 食生活や抗生物質の乱用が原因。
病原菌増加型(Pathobiont expansion)
ストレスや炎症が誘発。
機能低下型(Functional dysbiosis)
酪酸などの代謝産物が産生されなくなる。
対策の方向性(概要)
食生活の見直し(食物繊維の摂取増加、発酵食品)
抗生物質使用時の慎重な判断とプロバイオティクス併用
ストレスマネジメント、睡眠の質向上
運動習慣の確立
必要に応じた腸内フローラ検査(マイクロバイオーム解析)
各疾患と腸内フローラの乱れの関係について解説

腸内フローラの乱れが、どのような疾患の発症・進行と関連しているのかは、現在の腸内細菌学・免疫学・精神医学・代謝研究の中心的テーマの1つです。以下では、ディスバイオーシスの原因と、それによって引き起こされる代表的な疾患との因果関係・病態メカニズムを詳細に解説します。
1. 精神・神経系疾患(腸-脳相関)
関連する原因
慢性ストレス
睡眠不足
高糖質・高脂肪食
抗生物質使用
主な疾患
うつ病 / 不安障害
自閉症スペクトラム障害(ASD)
パーキンソン病
アルツハイマー病
メカニズム
腸内細菌が神経伝達物質(GABA、セロトニン、ドーパミン前駆体)を産生・調節。
ディスバイオーシスによりこれらの産生が減少し、情動・認知に影響。
炎症性サイトカインの増加(例:IL-6, TNF-α)により中枢神経系に神経炎症が波及。
腸漏れ(leaky gut) → 血中に毒素(LPS)が流入 → 神経炎症・脳機能障害へ
補足
自閉症の児童では、Clostridium属の異常増加、短鎖脂肪酸(特に酪酸)の欠乏が報告されています。
パーキンソン病では、腸内フローラの変化が病気の20年前から見られるという報告もあります。
2. 自己免疫疾患・アレルギー性疾患
関連する原因
抗生物質の過剰使用(特に幼少期)
帝王切開 / 人工栄養
過度な衛生環境(ハイジーン仮説)
食物繊維不足
主な疾患
アトピー性皮膚炎 / 気管支喘息
1型糖尿病
多発性硬化症(MS)
関節リウマチ
潰瘍性大腸炎 / クローン病(IBD)
メカニズム
幼少期の腸内フローラの構築に失敗すると、免疫寛容(自己や無害な物質を攻撃しない機能)が破綻。
短鎖脂肪酸(特に酪酸)はTreg(制御性T細胞)を誘導し、免疫の過剰反応を抑制する。
ディスバイオーシス → Tregの減少、Th17の過活性化 → 自己免疫の発症
補足
IBD患者では、抗炎症性菌(例:F. prausnitzii)が著しく減少。
関節リウマチ患者では、Prevotella copriの異常増加が確認されている。
3. 代謝性疾患
関連する原因
高脂肪・高糖質の西洋型食生活
運動不足
睡眠障害
抗生物質の影響
主な疾患
2型糖尿病
肥満
脂肪肝(NAFLD)
メタボリックシンドローム
メカニズム
ディスバイオーシスにより腸内細菌のエネルギー回収効率が高まり、エネルギー過剰吸収。
LPS(リポ多糖)が腸管から漏出し、慢性低度炎症(metaflammation)を引き起こす。
炎症がインスリン抵抗性を悪化させ、糖尿病へと進行。
短鎖脂肪酸(特にプロピオン酸・酢酸)の減少も代謝障害に関与。
補足
肥満者では、Firmicutes / Bacteroidetes比の増加が多く報告。
腸内細菌由来のTMAO(トリメチルアミンN-オキシド)は動脈硬化のリスク因子。
4. 感染症・過剰増殖症(SIBO)
関連する原因
抗生物質乱用
胃酸抑制剤(PPI)
小腸運動の低下
腸管手術後
主な疾患
C. difficile感染症
小腸内細菌過剰増殖症(SIBO)
カンジダ菌感染(Candida overgrowth)
メカニズム
善玉菌の減少により、病原菌の定着・異常増殖が可能になる(コロニゼーション・レジスタンスの破綻)。
SIBOでは、小腸に本来いない細菌が異常繁殖 → ガス・膨満感・下痢・吸収不良
C. difficileは、抗生物質による常在菌の破壊後に腸内で爆発的に増殖し、毒素産生 → 重篤な腸炎
5. 発達障害・行動障害(主に幼児期)
関連する原因
帝王切開
母乳育児の欠如
抗生物質投与(乳児期)
ビフィズス菌の減少
主な疾患
自閉症スペクトラム障害(ASD)
ADHD(注意欠陥・多動性障害)
メカニズム
腸内フローラが脳の発達やシナプス形成、神経伝達に影響。
母乳で育てられた乳児では、ビフィズス菌優勢な腸内環境が神経発達に有利。
ASD児ではClostridium属の増加、SCFA代謝の異常が報告される。
総括:原因と疾患の対応マトリクス
| 原因 | 関連疾患 | 主なメカニズム |
|---|---|---|
| 抗生物質の乱用 | C. difficile感染、IBD、ASD | 常在菌の破壊による病原菌増殖 |
| 食物繊維不足 | 2型糖尿病、肥満、アレルギー | 短鎖脂肪酸の減少、バリア機能低下 |
| 高脂肪・高糖質食 | 肥満、脂肪肝、うつ病 | LPS漏出、慢性炎症 |
| ストレス | うつ病、IBS、自己免疫疾患 | HPA軸活性化、炎症性菌増加 |
| 睡眠不足 | メタボ、認知障害 | 概日リズム破綻、腸内リズム崩壊 |
| 運動不足 | 肥満、腸炎 | 酪酸産生菌の減少、炎症 |
補足:ディスバイオーシス → 疾患 → 更なるフローラ悪化の悪循環
原因により腸内フローラが乱れる
免疫異常や炎症反応が起こり疾患が発症
疾患(例:炎症性腸疾患)の影響でさらに腸内フローラが悪化
治療薬(抗生物質、ステロイドなど)がさらに腸内環境に影響
→この悪循環を断ち切るために、腸内フローラの是正を治療の一環として重視する動きが強まっています。
腸内フローラの乱れを回復するための具体的な食事療法を詳しく解説

腸内フローラの乱れ(ディスバイオーシス)を回復・再構築するための食事療法は、腸内環境の科学的理解の進展により、かなり体系化されています。ここでは、最新の研究に基づいた、具体的かつ実践的な食事療法を段階的に、かつ専門的に解説します。
回復の基本方針:3つの柱
| 項目 | 目的 |
|---|---|
| プレバイオティクス(腸内細菌の餌) | 善玉菌の増殖・代謝活性を高める |
| プロバイオティクス(善玉菌そのもの) | 有益な菌を直接補充 |
| ポストバイオティクス(菌の代謝産物) | 炎症抑制・バリア強化・免疫調整 |
回復を目的とした食事療法のステップ・バイ・ステップ
□ステップ1:炎症性食品の除去(腸を休める)
〇避けるべき食品:
| 食品カテゴリ | 例 | 理由 |
|---|---|---|
| 加工食品 | ソーセージ、インスタント食品 | 乳化剤や保存料が腸粘膜を傷つける |
| 高脂肪・高糖質 | ファストフード、菓子 | 炎症性菌(例:Bilophila)の増加 |
| 人工甘味料 | アスパルテーム、サッカリン | 血糖コントロールを乱し、フローラ変化 |
| グルテン(場合による) | パン、パスタ | 腸漏れ(リーキーガット)促進の可能性 |
| アルコール | 特に蒸留酒・ビール | 腸管透過性を上げ、善玉菌を減らす |
□ステップ2:プレバイオティクス食品の積極摂取(善玉菌の餌)
プレバイオティクスとは:腸内細菌が発酵・代謝できる「非消化性炭水化物(主に食物繊維・オリゴ糖)」。
〇主な食品と成分
| 食材 | 含まれるプレバイオティクス成分 |
|---|---|
| 玉ねぎ、ニンニク、長ネギ | フルクタン、イヌリン |
| ごぼう、アスパラガス、菊芋 | イヌリン |
| バナナ(特に未熟なもの) | 難消化性でんぷん(レジスタントスターチ) |
| 大豆・納豆 | 大豆オリゴ糖 |
| 玄米、オートミール、もち麦 | β-グルカン、難消化性デンプン |
| 海藻(わかめ、昆布) | フコイダン、アルギン酸 |
〇効果
ビフィズス菌・ラクトバチルス属などの有益菌を選択的に増加させる。
短鎖脂肪酸(酢酸、酪酸、プロピオン酸)産生促進。
□ステップ3:プロバイオティクス食品の摂取(善玉菌の直接摂取)
プロバイオティクスとは:生きた有用菌を含む食品またはサプリメント。腸に届き、定着または一時的に効果を発揮。
〇主な食品と菌種
| 食品 | 含まれる菌種の例 |
|---|---|
| ヨーグルト(無糖) | Lactobacillus bulgaricus、Streptococcus thermophilus |
| 発酵乳(例:ケフィア) | 多種の乳酸菌 + 酵母 |
| 味噌・ぬか漬け・醤油(非加熱) | Bacillus subtilis(納豆菌)、Lactobacillus属 |
| 納豆 | 納豆菌(Bacillus subtilis) |
| キムチ・ザワークラウト | 乳酸菌(L. plantarumなど) |
〇効果
消化吸収の補助、免疫刺激、悪玉菌の抑制。
プロバイオティクスは「定着」しないが、「機能的作用」を持つ。
□ステップ4:ポストバイオティクスの産生促進(菌の代謝産物)
〇代表的なポストバイオティクス
酪酸(butyrate):大腸上皮のエネルギー源。抗炎症作用。
プロピオン酸、酢酸:腸内pHの低下、病原菌抑制。
〇酪酸菌を増やす食品
| 食品 | 効果のある菌 |
|---|---|
| レジスタントスターチ(未熟バナナ、冷やご飯) | 酪酸菌(Faecalibacterium prausnitzii) |
| 食物繊維(ごぼう、もち麦) | Roseburia属、Eubacterium属 |
| ポリフェノール(ブルーベリー、緑茶) | Akkermansia muciniphilaの増加促進 |
□ステップ5:腸のバリア強化を助ける栄養素の補給
| 栄養素 | 代表食品 | 働き |
|---|---|---|
| L-グルタミン | 鶏むね肉、卵、大豆 | 腸粘膜修復を促進 |
| 亜鉛 | カキ、赤身肉、卵 | 粘膜再生と免疫強化 |
| オメガ3脂肪酸 | 青魚、亜麻仁油 | 抗炎症作用、バリア強化 |
| ビタミンD | 鮭、きのこ、日光 | 免疫調整、腸管防御強化 |
| 発酵バター(ギー) | 酪酸供給源 | 上皮細胞の再生促進 |
具体的な1日の食事モデル(例)
| 食事 | メニュー例 | 目的 |
|---|---|---|
| 朝食 | 納豆 + 玄米 + 味噌汁(わかめ、豆腐入り) | プレ・プロ・ポストバイオティクス全部入り |
| 間食 | 未熟バナナ + 無糖ヨーグルト | 難消化性でんぷん + 生きた乳酸菌 |
| 昼食 | 鯖の塩焼き + もち麦ご飯 + 漬物 + ほうれん草のお浸し | 繊維・オメガ3・発酵食品の組み合わせ |
| 夕食 | キムチ鍋(野菜たっぷり) + 冷やしご飯 | 繊維・発酵食品・酪酸菌活性化 |
| 飲み物 | 緑茶、ルイボスティー | ポリフェノール・ノンカフェインで腸に優しい |
注意点と補足
プロバイオティクスサプリの選定は「菌株レベル」での臨床データがある製品を選ぶこと(例:Lactobacillus rhamnosus GGなど)。
初期にガス・膨満感などの副作用が出ることがある(特にSIBO持ち)。
個人の腸内環境によって効果は異なるため、腸内フローラ検査と併用すればより効果的。
医学的エビデンス(代表例)
| 試験 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 2018年 Nature誌(ヒトメタゲノム解析) | 高繊維食 vs 低繊維食 | 高繊維群で酪酸産生菌の増加・炎症マーカーの低下 |
| 2020年 Cell誌(ケフィア摂取) | ケフィア継続摂取 | 腸内乳酸菌の定着・NK細胞活性向上 |
| 2021年 Gut誌(ポリフェノール摂取) |
緑茶抽出物の摂取 | Akkermansia muciniphilaの増加・耐糖能改善 |
まとめ:食事療法の戦略
| アプローチ | 目的 |
|---|---|
| 不要な食品を「除去」 | 悪玉菌・炎症の抑制 |
| 必要な栄養を「補給」 | 善玉菌の育成、腸粘膜の回復 |
| 発酵・繊維・菌の三位一体を意識 | 長期的な腸内バランスの最適化 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は最近何かと話題になっている【腸内フローラ】について解説するコラムをお届けしてきました。
特に減量をしたいとしたときに体内環境、特に今回ご紹介した【腸内環境】は重要なキーワードになります。
今回、ご紹介した内容を元にご自身の【腸内環境】を見直してみてはいかがでしょうか?
腸内フローラの乱れを改善するための改善具体例もご紹介していますので、腸内環境の乱れがあると感じる場合には、是非、今回の内容を参考に実践してみてください!

- スマートウェイ/スタジオ/メディカルフィットネス小樽店
- スマートスタジオ/メディカルフィットネス平岡店
- スマートウェイ平岸店
所属の健康運動指導士トレーナー竹村です。
内科系疾患・整形外科疾患・予備軍の方に向けた健康増進施設、指定運動療法施設にてトレーナー従事中
運動を行う上での効果やポイント、身体についての知識など、運動に関わる様々な情報を発信していきます。







