暑い夏を乗り切る!夏バテについて徹底解説!【前編】夏バテの原因・冷たいものを食べ過ぎるとどうなってしまうのか?

北海道でも30度を超える高い気温の日が増えて、夏バテをしているという方も多いのではないでしょうか?
まだまだこれから気温が高くなりそうな夏ですが、今回は暑い時には気を付けたい【夏バテ】について徹底解説をしていきます。
- 暑さのせいで最近なんだか体調がすぐれない
- 夏バテのようになっている
など夏の暑さによって体調がすぐれない方は特に!最後までご覧ください!!
▼この記事を読んで欲しい方
- 夏バテになってしまっている方
- 夏バテになりたくない方
- 夏バテの対策を知りたい方
- 夏バテとはどのようなものなのかを知りたい方
- 夏の暑さに負けない身体を手に入れたい方
- 暑さに弱い方
- 夏の対策について知りたい方
- なぜ夏バテになってしまうのかを知りたい方
- 最近冷たい物ばかりを食べている方
- 夏に冷たいものを多く摂ってしまう方
▼この記事を読んで分かること
- 夏バテになる原因について解説
- 暑い時に冷たいものを食べたくなる理由について
- 冷たいものばかりを食べることで起こる身体への影響について
- 夏バテの対策について解説
- 食欲が湧かないときの対策・改善方法について
- 身体が冷えてしまうときの対策・改善方法について
- 倦怠感があるときの対策・改善方法について
なぜ夏バテになるのか解剖学的に詳しく解説
夏バテ(英語では "summer fatigue")は、高温多湿な環境によって体内の恒常性(ホメオスタシス)が崩れることで起きる全身性の不調です。
解剖学的・生理学的には、自律神経系、内分泌系、消化器系、循環系、体温調節中枢などが複雑に関与しています。
以下で、夏バテの発症メカニズムを解剖学的視点で詳しく解説します。
1.自律神経の乱れ(交感神経と副交感神経)
◉ 関係部位
視床下部(hypothalamus):自律神経の統合中枢
脊髄交感神経節・迷走神経(副交感)
◉ どう乱れるのか?
夏は外気温が高く、体温調節のために交感神経が過剰に働く
一方で、冷房の効いた室内との気温差が大きくなると、副交感神経が優位になりすぎたりして、交感・副交感のバランスが崩れる
結果、だるさ、頭痛、めまい、食欲不振などが出現
◉ 解剖学的ポイント
自律神経は中枢(視床下部)→脊髄(T1〜L2)交感神経節 → 各臓器というルートで支配
特に消化器官(胃・腸)は副交感神経(主に迷走神経)でコントロールされており、乱れると消化力低下
2.体温調整中枢の負荷
◉ 関係部位
視床下部 前部(前視床下部):体温調節中枢
汗腺、皮膚血管、骨格筋
◉ どうなるのか?
暑さにより、発汗や血管拡張が過剰に起こる → 体液やミネラル(Na⁺、K⁺)の喪失
大量の汗で脱水・電解質バランスが崩れる
血液量の低下により、脳・腎・肝への血流が減少し、全身の代謝も落ちる
3.ホルモンバランスの乱れ(視床下部ー下垂体ー副腎系)
◉ 関係部位
視床下部 → 下垂体 → 副腎皮質軸(HPA軸)
副腎皮質ホルモン:コルチゾール、アルドステロン
◉ どうなるのか?
長時間のストレス(暑さ・脱水など)により、HPA軸が疲弊
アルドステロンの分泌低下 → Na⁺再吸収低下 → さらに脱水へ
コルチゾール低下 → エネルギー生成能力の低下 → 倦怠感
4.消化器系の機能低下
◉ 関係部位
胃、腸、膵臓、肝臓などの消化器官
迷走神経(副交感神経)
◉ どうなるのか?
暑さ・自律神経の乱れで副交感神経がうまく働かず、胃腸の運動や分泌が低下
結果:
胃もたれ
食欲不振
下痢または便秘
5.循環系への影響(低血圧・貧血)
◉ 関係部位
心臓、血管系、自律神経系
腎臓(RAA系:レニン・アンジオテンシン・アルドステロン)
◉ なぜ起きるか?
暑さ→血管拡張→血圧低下
発汗→循環血液量減少
さらに、冷房で皮膚血管が急に収縮すると、血圧調整が間に合わず、めまいや立ちくらみ
夏バテの総合メカニズム(解剖学的ルート)
1.高温・多湿
↓
2.視床下部(体温調節・自律神経・内分泌中枢)が過剰に働く
↓
3.交感・副交感神経のバランス崩壊 + ホルモン調整不能
↓
4.消化機能低下・脱水・代謝低下・全身の倦怠感
↓
5.夏バテの症状(だるさ、食欲不振、頭痛、下痢、冷えなど)
予防のための医学的アプローチ(解剖学的な視点)
| 対策 | 解剖学的根拠 |
|---|---|
| 水分+電解質補給 | 脱水予防、血漿量維持 → 脳・腎の血流確保 |
| 冷房と外気の温度差を少なくする | 自律神経の急激な切り替え負荷を軽減 |
| 腸を温める(温かい食事) | 消化器官の血流を促進、副交感神経優位 |
| 睡眠の質を確保 | 視床下部のリズム回復、ホルモン分泌(メラトニンなど)に寄与 |
| 適度な運動(軽いウォーキングなど) | 自律神経のリズム訓練、筋ポンプ作用による循環改善 |
気温が高いと冷たいものを食べたくなるのはなぜ?解剖学的に細かく説明
気温が高いと冷たいものを欲するのは、生理的・解剖学的に見ると、体温調節中枢・感覚神経・口腔・消化管の温度受容器などが連携して働くからです。以下、解剖学的・生理学的観点から詳しく説明します。

1.視床下部と体温調整中枢のはたらき
関係部位:視床下部(hypothalamus)
役割:体温の恒常性(homeostasis)を維持する中枢
高温環境では、視床下部の体温調節中枢(前視床下部:anterior hypothalamus)が働いて、体温を下げようとします。これにより以下の反応が起こります:
発汗の促進(汗腺を刺激)
皮膚血管の拡張(熱放散を促進)
冷却行動の動機づけ(=冷たいものを求める)
これは本能的行動で、視床下部からの指令により、快・不快の感覚を伴って冷たい物を選択しやすくなります。
2.温度受容体(Thermoreceptors)による感覚の入力
関係部位:皮膚、口腔、咽頭、消化管などの末梢神経
受容体の種類
TRPV1:高温を感知(42℃以上)
TRPM8:冷感を感知(〜15~25℃)← ミントの成分メントールが刺激するのもこれ
冷たい物を摂取すると
口腔・咽頭のTRPM8受容体が刺激されて「冷たい」と感じる
その刺激が三叉神経(CN V)や舌咽神経(CN IX)などを通って脳幹に伝達
冷却感=「気持ちいい」「快適」という報酬系(側坐核など)の活性化にもつながる
3.消化管の温度感知と快感の形成
関係部位:胃・腸の内壁(特に迷走神経の終末)
冷たい物が胃に入ると、胃の温度が一時的に下がり、迷走神経(CN X)を介して視床下部や脳幹にフィードバック
結果、視床下部は「体温が少し下がった」と認識 → 心地よさが増す
4.報酬系(脳内ドーパミン系)の関与
関係部位:側坐核(nucleus accumbens)、腹側被蓋野(VTA)
冷たい物=「快適」な感覚は、報酬系に作用してドーパミンを放出
このことで、冷たい物を食べることが学習され、欲求として強化される(=習慣化)
まとめ:解剖学的ルートで見る「冷たい物を欲する流れ」
1.気温上昇
2.→ 視床下部(体温調節中枢)が「冷却行動」を促す
3.→ 皮膚・口腔・消化管の温度受容器が冷たい物に反応
4.→ 感覚神経(特に三叉神経、舌咽神経、迷走神経)が脳へ信号を伝える
5.→ 脳内報酬系(側坐核など)が活性化し、「冷たい=気持ちいい」と学習
6.→ 冷たい物を積極的に摂ろうとする行動が起こる
補足:行動としての「飲食」は高次脳機能とも関係
前頭前野や扁桃体も、「快」「不快」の判断や意欲に関与しています
暑い日には「冷たいアイスが食べたい」という意思決定も、この高次脳の働きの一部です
暑い日に冷たい物ばかりを食べるとどうなるか詳しく解説
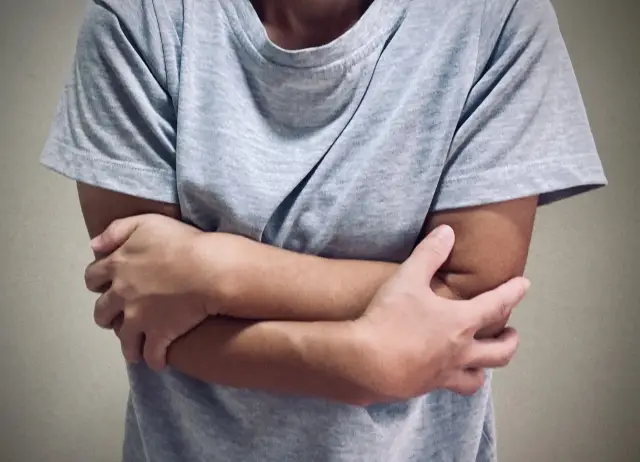
暑い日に冷たい物ばかりを食べると、一時的には涼しく感じられますが、体にはいくつかの悪影響が出る可能性があります。以下にその詳細を説明します。
1.胃腸のはたらきが低下する
冷たい物を多く摂取すると、胃や腸の血流が悪くなり、消化機能が落ちます。
症状の例:食欲不振、胃もたれ、下痢、腹痛
理由:胃腸は37℃前後の体温に適した環境で働いていますが、冷たい物で内臓温度が下がると、消化酵素の働きが鈍くなります。
2.自律神経が乱れる
冷たい物の摂りすぎで体の内側と外側の温度差が大きくなると、自律神経が混乱します。
症状の例:だるさ、頭痛、めまい、睡眠障害
理由:自律神経は体温調整や内臓の働きを司っていますが、冷たい刺激が続くと交感神経と副交感神経のバランスが崩れます。
3.代謝が低下する
体が冷えると、エネルギーを燃やす機能(基礎代謝)が落ちます。
結果:太りやすくなる、疲れやすくなる
理由:代謝が低下すると、エネルギー消費量が減り、脂肪がたまりやすくなります。
4.免疫力が低下する
体温が下がると、免疫細胞の働きも鈍くなります。
結果:風邪をひきやすくなる、感染症にかかりやすくなる
理屈:免疫細胞(特に白血球)は体温36.5℃〜37℃の環境で活発に働きます。冷えた体内では活動が鈍化します。
5.女性特有の冷え性・月経不順の悪化
冷たい物による体の冷えは、特に女性にとって大きな影響があります。
結果:生理痛の悪化、月経不順、手足の冷え
理由:冷えにより骨盤内の血流が悪くなるため。
対策・バランスのとり方
冷たい物は1日に1〜2回までに。
食べる前に常温に少し戻す。
冷たい物を摂ったら、温かい飲み物や汁物で中和する。
エアコンによる外部の冷えにも注意する。
まとめ
| リスク | 主な影響 |
|---|---|
| 胃腸機能の低下 | 下痢、食欲不振など |
| 自律神経の乱れ | 倦怠感、めまい、睡眠不良など |
| 代謝・免疫の低下 | 太りやすい、風邪をひきやすい |
| 女性特有の症状悪化 | 生理不順、冷え症など |
暑い日こそ「冷たい物+温かい物」のバランスが大切です。体の内側は意外と冷えやすいので、意識的に温めるようにしましょう。冷たい飲食物は楽しみつつ、体への影響も考えて摂取するのがおすすめです。
ここまでは
- 夏バテになる原因について解説
- 暑い時に冷たいものを食べたくなる理由について
- 冷たいものばかりを食べることで起こる身体への影響について
をまとめてお伝えしてきました。後編では、【夏バテの対策】を詳しく解説していきます!是非、後編も併せてご覧ください!

- スマートウェイ/スタジオ/メディカルフィットネス小樽店
- スマートスタジオ/メディカルフィットネス平岡店
- スマートウェイ平岸店
所属の健康運動指導士トレーナー竹村です。
内科系疾患・整形外科疾患・予備軍の方に向けた健康増進施設、指定運動療法施設にてトレーナー従事中
運動を行う上での効果やポイント、身体についての知識など、運動に関わる様々な情報を発信していきます。







