暑い夏を乗り切る!夏バテについて徹底解説!【後編】夏バテの対策を症状に合わせてご紹介!

【夏バテ】と聞くと自分もかもしれない…そんな風に感じる方も多いのではないでしょうか?
前編では
- 夏バテとはそもそもどのような状態のものを指すのか?
- 暑い時に冷たいものを食べたくなる仕組みはどのようなものなのか?
という部分を詳しくまとめてお伝えしていきました。
後編では
- 夏バテの対策について解説
- 食欲が湧かないときの対策・改善方法について
- 身体が冷えてしまうときの対策・改善方法について
- 倦怠感があるときの対策・改善方法について
より具体的にご紹介していきます。気になるという方は是非、最後までご覧ください!!
▼この記事を読んで欲しい方
- 夏バテになってしまっている方
- 夏バテになりたくない方
- 夏バテの対策を知りたい方
- 夏バテとはどのようなものなのかを知りたい方
- 夏の暑さに負けない身体を手に入れたい方
- 暑さに弱い方
- 夏の対策について知りたい方
- なぜ夏バテになってしまうのかを知りたい方
- 最近冷たい物ばかりを食べている方
- 夏に冷たいものを多く摂ってしまう方
▼この記事を読んで分かること
- 夏バテになる原因について解説
- 暑い時に冷たいものを食べたくなる理由について
- 冷たいものばかりを食べることで起こる身体への影響について
- 夏バテの対策について解説
- 食欲が湧かないときの対策・改善方法について
- 身体が冷えてしまうときの対策・改善方法について
- 倦怠感があるときの対策・改善方法について
夏バテを対策する方法を徹底解説

夏バテ対策は、自律神経の調整・栄養の最適化・体温調節・睡眠管理など、多角的に行う必要があります。以下に、医学的・生理学的根拠に基づいた夏バテ対策8選を徹底解説します。
1.こまめな水分・電解質補給
▶︎ なぜ重要?
暑さで汗をかくと、水分とともにNa⁺(ナトリウム)などの電解質も失われる
脱水により血液量が減少 → 脳・腎・消化器の血流低下 → 倦怠感や消化不良
▶︎ 実践ポイント
喉が渇く前に飲む(1日1.5〜2Lが目安)
経口補水液(ORS)や麦茶+塩などでミネラルも補給
カフェイン・アルコールは利尿作用が強く、過剰摂取はNG
2.3食しっかり食べて胃腸を整える
▶︎ なぜ重要?
自律神経の乱れや冷たい物の摂りすぎで胃腸機能が低下する
食べない → エネルギー不足 → 倦怠感・筋力低下
▶︎ 実践ポイント
朝食は絶対に抜かない(体内時計と消化リズムを整える)
冷たいもの中心にしない:温かい汁物、消化のよい炭水化物、たんぱく質を意識
発酵食品(納豆・味噌・ヨーグルト)で腸内環境も改善
3.睡眠の質を高める(自律神経の回復)
▶︎ なぜ重要?
睡眠中に副交感神経が優位となり、自律神経のリズムを整える
成長ホルモンやメラトニン分泌で、身体の修復が促される
▶︎ 実践ポイント
就寝前2時間はスマホや強い光を避ける(ブルーライトは交感神経を刺激)
エアコンは27〜28℃・湿度50〜60%に設定(体を冷やしすぎない)
寝る1〜2時間前に38~40℃のぬるめの風呂に入ると、入眠がスムーズ
4.冷房の使い方に注意(外気との温度差)
▶︎ なぜ重要?
外気との温度差が5℃以上になると、交感神経と副交感神経の切り替えが追いつかない
結果、めまいや頭痛、倦怠感につながる
▶︎ 実践ポイント
冷房の温度設定は26〜28℃に
冷風が直接当たらないように風向きを調整
外出時は羽織るもの(カーディガン、スカーフなど)で自律神経の過負荷を軽減
5.日中の過度な運動(ウォーキング・ストレッチ)
▶︎ なぜ重要?
適度な運動は、自律神経のリズム回復と血流改善に役立つ
筋肉を動かすことで、熱の放散効率もアップ
▶︎ 実践ポイント
夕方〜夜の比較的涼しい時間帯に20〜30分のウォーキング
冷房の効いた室内でのストレッチやラジオ体操も効果的
運動後は必ず水分補給
6.ビタミン・ミネラルを意識した食事
▶︎ なぜ重要?
汗とともに失われるカリウム・マグネシウム・ビタミンB群・ビタミンCの不足は、疲労感や筋肉の痙攣を招く
▶︎ 実践ポイント
ビタミンB群(豚肉、玄米、卵):エネルギー代謝を助ける
ビタミンC(果物、ピーマン、ブロッコリー):抗酸化・免疫維持
カリウム(バナナ、スイカ、きゅうり):筋肉・神経の興奮を調整
マグネシウム(豆類、海藻、ナッツ):自律神経の安定に重要
7.冷たいもの・刺激物の摂取を控えめに
▶︎ なぜ重要?
冷たい物の摂りすぎは胃腸を冷やし、消化機能が低下
刺激物(辛い物、アルコール)は交感神経を過剰に刺激
▶︎ 実践ポイント
アイス・冷たい飲料は1日1〜2回までに
「冷やし中華」や「そうめん」なども、温かい汁物を一緒に取るとよい
常温の水や麦茶、温かい白湯を日常的に飲むのがおすすめ
8.メンタルケア(ストレスマネジメント)
▶︎ なぜ重要?
精神的ストレスも交感神経を過剰に働かせ、自律神経失調や胃腸症状を悪化
暑さによる不快感が、イライラ・不眠・疲労感に直結する
▶︎ 実践ポイント
深呼吸、瞑想、音楽、読書など副交感神経を刺激する時間を意識的に作る
趣味や軽い運動、自然の中で過ごす時間が心身に効果的
1人で抱え込まず、話す・共有することも重要
まとめ表:夏バテ8つの徹底対策とポイント
| 対策 | 内容 | 解剖学的視点 |
|---|---|---|
| 1. 水分・電解質補給 | 脱水防止、血流維持 | 血漿量、腎・脳の血流保持 |
| 2. 3食の食事 | 胃腸の負担軽減 | 消化器の副交感神経支配 |
| 3. 質の良い睡眠 | 自律神経調整、ホルモン分泌 | 視床下部の調整機能 |
| 4. 冷房温度管理 | 自律神経の急変を防ぐ | 温度受容体と自律反射 |
| 5. 適度な運動 | 血流・代謝・自律神経刺激 | 筋ポンプ、交感神経刺激 |
| 6. 栄養バランス | ミネラル・ビタミンで代謝を回復 | 代謝酵素、神経伝達補助 |
| 7. 冷たいものを控える | 胃腸冷却を防ぐ | 内臓温度と消化酵素活性 |
| 8. メンタルケア | ストレスによる交感神経亢進を抑制 | HPA軸の抑制、迷走神経活性化 |
どの対策も、「体内の恒常性(ホメオスタシス)を維持する」という点で共通しています。
食欲が湧かないときの対策を徹底解説

食欲不振は、特に夏場は高温・脱水・自律神経の乱れ・胃腸の冷えなどが原因で起こりやすい症状です。
解剖学・生理学的な観点を踏まえながら、食欲不振を改善するための具体的な対策を以下に詳しく解説します。
食欲不振の原因まとめ(夏場の場合)
| 原因 | 解説 |
|---|---|
| 自律神経の乱れ | 暑さや温度差で交感神経優位 → 胃腸の血流低下・運動低下 |
| 胃腸の冷え | 冷たい物の摂りすぎ → 胃酸分泌・蠕動運動が低下 |
| 脱水・ミネラル不足 | 胃液や消化酵素の分泌低下につながる |
| 精神的ストレス | 視床下部や扁桃体の影響で、食欲中枢が抑制される |
食欲不振を改善するための7つの対策
1. まずは温かい食べ物・飲み物を取り入れる
▸ 理由
温かいものは胃腸の血流を促進し、副交感神経を優位にして消化を促す
▸ 実践例
味噌汁、野菜スープ、白湯、煮物
朝起きたら白湯を一杯飲むのも効果的
2. 食べやすい「さっぱり×消化に良い」メニューにする
▸ 理由
消化に負担をかけずに栄養を吸収するのが重要
冷たい物よりも「常温+柔らかい物」がおすすめ
▸ 実践例
おかゆ、雑炊、豆腐、そうめん+温かいだし汁
梅干し、レモン、シソなどの香味野菜で唾液・胃液を刺激
3. 1日3食にこだわらず「小分けに頻回食」する
▸ 理由
少量ずつ食べることで、胃腸への負担を軽減しつつエネルギー補給できる
▸ 実践例
朝:バナナ+ヨーグルト
昼:そうめん+温かいだし
間食:おにぎり1個や豆乳
夜:やさしい味の煮物など
4. 香りやスパイスで「食欲中枢」を刺激する
▸ 理由
食欲中枢(視床下部)や唾液腺を刺激することで、胃腸も活性化
▸ 実践例
生姜、にんにく、シソ、ミョウガ、山椒
エスニック料理やカレー(辛すぎない範囲で)
5. ビタミンB群・亜鉛を意識して摂取
▸ 理由
ビタミンB群は代謝と胃腸の粘膜維持に関与
亜鉛は味覚の維持・食欲中枢の刺激に関係
▸ 実践例
ビタミンB群:豚肉、納豆、卵、玄米、バナナ
亜鉛:牡蠣、レバー、かつお節、ナッツ類
6. しっかり睡眠・軽い運動で自律神経を整える
▸ 理由
視床下部のバランスを回復させ、胃腸の動きが改善される
▸ 実践例
夜は最低6〜7時間の睡眠を確保
軽いウォーキングやストレッチで血流と副交感神経の刺激を促進
7. 薬やサプリを適切に使う(必要な場合)
▸ 理由
一時的に消化機能を助けるため、薬の補助も有効なことがある
▸ 実践例
消化酵素(ビオフェルミン・新ビオフェルミンSなど)
胃薬(大建中湯など漢方系もおすすめ)※医師・薬剤師に相談
食欲のコントロールに関わる脳部位(補足)
| 脳部位 | 働き |
|---|---|
| 視床下部 | 食欲中枢・満腹中枢を統括、自律神経と連携 |
| 扁桃体 | ストレスや不快感による食欲抑制 |
| 大脳皮質(前頭前野) | 食の好み・意欲など高次的な判断 |
食欲不振対策まとめ表
| 対策 | 目的 | ポイント例 |
|---|---|---|
| 温かい食事・飲み物 | 胃腸を温め活性化 | 白湯、味噌汁、煮物など |
| 消化に良い食事 | 胃腸への負担軽減 | おかゆ、豆腐、そうめん |
| 少量頻回食 | エネルギー補給維持 | 1日5〜6回、小分けに |
| 香味・スパイス | 食欲中枢刺激 | シソ、しょうが、梅干し |
| 栄養補給 | 消化器や代謝を支える | ビタミンB群、亜鉛など |
| 睡眠・運動 | 自律神経安定化 | ストレッチ・7時間睡眠 |
| 必要に応じて薬 | 消化・腸内環境サポート | 胃薬・消化酵素など |
症状が長引く、食事がほとんど取れない、体重が急減した場合は、内科または消化器内科の受診も検討してください。
冷えの対策を徹底解説
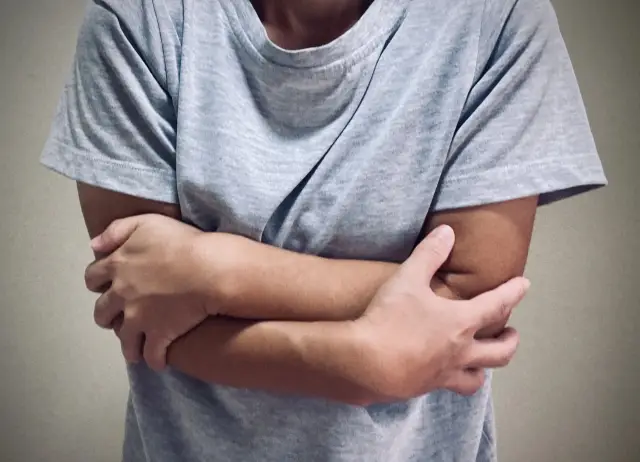
「冷え」の対策は、単に「体を温める」だけではなく、自律神経・血流・筋肉量・ホルモン・内臓機能など、体全体のバランスを整えることがカギになります。
特に女性や夏の冷房下では末梢血管の収縮・筋肉量の低下・自律神経の乱れなどが原因となって「冷え性」につながりやすいです。
ここでは、解剖学的・生理学的な視点をもとにした冷えの対策8選を詳しく解説します。
冷えの原因をおさらい(体の中で何が起きているか)
| 原因 | 解説(解剖学的視点) |
|---|---|
| 自律神経の乱れ | 視床下部による体温調節がうまくいかず、末梢血管が収縮しやすくなる |
| 筋肉量の少なさ | 筋肉は「熱産生」の主要器官。特に下半身の筋量が少ないと冷えやすい |
| 血流障害 | 毛細血管の収縮、低血圧、貧血などで末梢(手足)に血が届かない |
| ホルモンバランスの乱れ | 女性ホルモン(エストロゲン)低下で血管の反応が悪くなる |
| 食生活の乱れ | エネルギー不足、鉄分・ビタミン不足で代謝が低下 |
| 冷えの環境 | 冷房・薄着・冷たい飲食物などによる外的な冷却刺激 |
冷え対策 8選【医学的に効果的】
1. 下半身を中心に温める(特に足首・ふくらはぎ)
▶︎ 理由
足元は末梢血管が密集し、体温低下の影響を最も受けやすい
ふくらはぎ=「第二の心臓」として血液循環を助ける筋肉が集中
▶︎ 実践方法
レッグウォーマー、靴下、足湯(40℃・15〜20分)
お風呂上がりに冷たい床を素足で歩かない
2. 温かい食事と飲み物をとる(内臓から温める)
▶︎ 理由
胃腸・腎臓・肝臓など内臓の温度が下がると、内臓血流が減り代謝が低下
副交感神経が抑制され、消化機能も悪化 → 慢性冷えに
▶︎ 実践方法
白湯、生姜湯、味噌汁、根菜たっぷりスープ
飲み物・食べ物は「冷やしすぎない」ことが基本(常温以上)
3. 筋肉を増やす(特に下半身)
▶︎ 理由
筋肉は体熱の40%以上を産生
特に大腿・臀部・ふくらはぎは熱産生が高い
▶︎ 実践方法
スクワット・階段の上り下り・軽いジョギング
デスクワーク中もつま先上げ・ふくらはぎポンプ運動
4. 腹巻・カイロなどで「体幹」を冷やさない
▶︎ 理由
お腹・腰回りの臓器は血流が集中しているため、全身が冷えやすくなる
骨盤内の臓器(腸・子宮・膀胱など)は温度に敏感
▶︎ 実践方法
腹巻き、カイロ(仙骨・おへそ下・腰)
カイロは「肩甲骨の間」や「首の後ろ」も効果的(自律神経支配部位)
5. お風呂で体の芯まで温める(シャワーではNG)
▶︎ 理由
湯船につかることで深部体温が上昇し、血流・自律神経が整う
交感神経から副交感神経への切り替えが促進され、リラックス効果も得られる
▶︎ 実践方法
38〜40℃のお湯に15〜20分
入浴後はすぐに足元とお腹を保温
6. 鉄分・たんぱく質・ビタミンをしっかり摂る
▶︎ 理由
鉄不足(隠れ貧血)は血液の酸素運搬能力を下げ、冷えの大きな要因に
タンパク質・ビタミンB群は熱産生と代謝に必須
▶︎ 実践方法
鉄分:赤身肉、レバー、小松菜、ひじき
タンパク質:卵、魚、大豆、鶏むね肉
ビタミンB群:豚肉、玄米、納豆、にんにく
7. 冷房と服装のバランスを調整する
▶︎ 理由
冷房による皮膚冷却が続くと、末梢血管が慢性的に収縮しやすくなる
首・手首・足首の「三つの首」を冷やすと、熱の逃げ場になってしまう
▶︎ 実践方法
薄手のカーディガン・スカーフ・レッグウォーマーを活用
冷房温度は26〜28℃、扇風機の風が直接当たらないように
8. 自律神経を整える生活習慣
▶︎ 理由
冷え性の根本原因は多くが自律神経のバランス不良
交感神経過多状態では末梢の血流が抑制される
▶︎ 実践方法
睡眠:毎日同じ時間に就寝・起床(7時間が目安)
深呼吸、瞑想、ゆったりした時間を取る
カフェイン・スマホは夜控える
まとめ:冷え対策の全体像
| 分類 | 対策 | キーワード |
|---|---|---|
| 血流改善 | 足湯・筋トレ・温浴 | ふくらはぎポンプ、第二の心臓 |
| 内臓温め | 温かい食事・腹巻 | 消化器系の血流UP |
| 代謝サポート | 鉄・たんぱく・ビタミンB群 | 酵素・赤血球機能 |
| 環境調整 | 冷房・服装の工夫 | 三首を冷やさない |
| 神経調整 | 睡眠・リラックス | 視床下部・副交感神経 |
倦怠感の対策を徹底解説

倦怠感(けんたいかん)とは、「体がだるい」「疲れて何もしたくない」「頭が重い」「やる気が出ない」といった状態の総称で、肉体的・精神的・神経的な疲労が重なって起こります。
特に夏場の倦怠感は、高温・脱水・栄養不足・自律神経の乱れなどが原因で起きやすく、慢性化すると夏バテやうつ症状に進展することもあります。
倦怠感の原因(解剖学・生理学的視点)
| 原因 | 内容 | 関連器官・仕組み |
|---|---|---|
| 自律神経の乱れ | 暑さ・ストレスなどで交感神経過多 → 疲労が取れにくくなる | 視床下部、自律神経系 |
| 栄養不足 | 糖質・たんぱく質・ビタミン不足でエネルギー代謝が落ちる | ミトコンドリア、肝臓 |
| 脱水・電解質不足 | 細胞内外の浸透圧異常で筋肉・神経の働きが低下 | ナトリウム、カリウム、腎臓 |
| 睡眠の質の低下 | 睡眠中の回復が不十分 → ホルモン分泌不全 | メラトニン、成長ホルモン |
| 筋肉量低下・運動不足 | 筋肉が減ると代謝も下がる → 疲れやすく | 骨格筋、ミトコンドリア |
| 精神的ストレス | コルチゾール過剰で神経疲労・集中力低下 | HPA軸(視床下部-下垂体-副腎) |
倦怠感の対策【8つの医学的アプローチ】
1. 水分+電解質をこまめに補給する
▶︎ なぜ?
脱水やナトリウム・カリウムの不足は、筋肉や神経の働きを低下させる
倦怠感・頭痛・疲労感の直接的原因になる
▶︎ どうする?
水だけでなく、麦茶+塩、経口補水液、スポーツドリンク(薄めて)を活用
朝起きたらまず1杯の白湯 or 常温水を飲む
2. 3食しっかり+ビタミンB群とたんぱく質を補給
▶︎ なぜ?
倦怠感=「エネルギーが作れていない状態」
特にビタミンB1(糖代謝)・B2(脂質代謝)・B6(たんぱく代謝)は重要
▶︎ どうする?
豚肉、卵、納豆、玄米、魚介、豆腐を積極的に摂取
夏野菜(トマト・ピーマン・ナスなど)も抗酸化+整腸に◎
3. 軽い運動で血流と代謝をアップ
▶︎ なぜ?
軽い運動は筋肉からミトコンドリアの働きを高めて、疲れにくい体に
自律神経も整い、心身が軽くなる
▶︎ どうする?
ウォーキング、ラジオ体操、ストレッチなど1日15〜30分
筋トレ(スクワット、腹筋)は週に2〜3回でもOK
4. 温かい風呂で副交感神経を回復させる
▶︎ なぜ?
交感神経(緊張モード)→副交感神経(休息モード)への切り替えで疲労回復が進む
シャワーだけでは深部体温が上がらず、疲れが抜けにくい
▶︎ どうする?
38〜40℃のお風呂に15分以上つかる
入浴後は冷やさずに「靴下+腹巻」で保温
5. しっかり眠る(睡眠の質を最優先)
▶︎ なぜ?
睡眠中に成長ホルモン、メラトニンが分泌 → 細胞の修復&自律神経の回復
寝不足は倦怠感の最も大きな要因の1つ
▶︎ どうする?
就寝1時間前はスマホ・強い光NG
エアコンは27℃前後、湿度は50〜60%に保つ
6.5時間以上、できれば毎日同じ時間に寝起きする
6. 冷たいものを控える(胃腸の冷えは全身の疲れ)
▶︎ なぜ?
冷たい飲食物で胃腸が冷えると、消化・吸収が低下
栄養が足りなくなり、慢性的なだるさへ
▶︎ どうする?
冷たいものは1日1〜2回までに
常温の飲み物、温かいスープ・味噌汁を取り入れる
胃もたれする場合は「よく噛む・少量ずつ食べる」が基本
7. 鉄分や亜鉛を意識して摂る(隠れ貧血対策)
▶︎ なぜ?
鉄欠乏性貧血・亜鉛欠乏は、酸素不足や酵素反応の低下を引き起こし、だるさの原因に
▶︎ どうする?
鉄:赤身肉、レバー、小松菜、あさり
亜鉛:牡蠣、チーズ、ナッツ、卵
ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ(例:鉄+ブロッコリー)
8. 精神的ストレスを減らす(コルチゾールを抑える)
▶︎ なぜ?
慢性ストレスで副腎が疲れる(=アドレナル・ファティーグ)
コルチゾールが乱れると、眠れず・やる気も出ず、倦怠感が強まる
▶︎ どうする?
無理に頑張らず「余白をつくる」
音楽・読書・散歩・自然の中で過ごす
自分の感情を外に出す(人に話す・日記を書く)
倦怠感対策まとめ表
| 分類 | 対策 | ポイント |
|---|---|---|
| 水分・電解質補給 | 脱水対策 | 経口補水液、麦茶+塩 |
| 栄養補給 | エネルギー代謝回復 | ビタミンB群、鉄、亜鉛、たんぱく質 |
| 胃腸のケア | 栄養吸収サポート | 冷たい物を控え、温かい食事 |
| 睡眠 | 自律神経・ホルモン回復 | 就寝前のスマホNG、40℃入浴 |
| 運動 | 血流・代謝活性化 | ストレッチ、ウォーキング |
| 入浴 | 深部体温を上げる | 湯船に15分以上つかる |
| ストレス管理 | 精神的疲労を減らす | 瞑想、自然、音楽 |
受診が必要な倦怠感のサイン(要注意)
休んでも回復しない、2週間以上続く
動悸・息切れ・めまいを伴う
明らかな体重減少やうつ傾向がある
→ 内科・心療内科・内分泌科などの受診をおすすめします
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は2つのコラムに渡って【夏バテ】についてまとめてご紹介してきました。
近年の中でも特に暑い夏になっていますが、【夏バテ】にならないように対策をすることで健康に夏を過ごすことはできます。今回ご紹介した内容を参考にしながら健康的に夏を過ごしていただけると嬉しいです。
暑い夏にバテずに動き続けるためには【体力】も必要です。【体力】をつけるためにはあなたにあった運動を無理なく継続することが必要です。
そんな時にオススメなのは
- スマートスタジオ
- スマートウェイ
のパーソナルトレーニング!!
完全パーソナル対応で、コーチがあなたにあった運動をご提供します。更に、パーソナル対応なので、その日の身体の状態に合わせてメニューの変更も可能!!
現在、スマートウェイ・スマートスタジオ各店では入会キャンペーンを強化中!
まずはお近くの店舗で体験レッスンを受けてみませんか?今しかないチャンスをお見逃しなく!!
皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております!

- スマートウェイ/スタジオ/メディカルフィットネス小樽店
- スマートスタジオ/メディカルフィットネス平岡店
- スマートウェイ平岸店
所属の健康運動指導士トレーナー竹村です。
内科系疾患・整形外科疾患・予備軍の方に向けた健康増進施設、指定運動療法施設にてトレーナー従事中
運動を行う上での効果やポイント、身体についての知識など、運動に関わる様々な情報を発信していきます。







